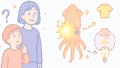毎朝、太陽の光で目が覚めたり、窓から差し込む日差しで部屋が明るくなったりするのって、当たり前のことだけど、光にはたくさんの不思議が隠れています。
見える光だけでなく、目に見えない光、光の速さ、そして光を通したり、曲がったり、反射したり…そういう性質のおかげで私たちは世界を見たり、色を楽しめています。
光の基本的な性質と不思議なポイント
この世の中には、「光って何だろう?」「どうして空は青いの?」「どうして虹ができるの?」など、ふだん疑問に思わないようなことにも、科学を知るとその秘密がわかります。
今日はその中でも、小学生にもわかる「光の不思議」について説明しながら、ちょっと変わった発明や、光について学べる場所をご紹介したいと思います。
光は波であり、粒子でもある
光は「電磁波」の一種で、波の性質を持っています。
でも同時に「光子」という粒のような性質もあり、量が多ければ明るく、少なければ暗く見えます。
光はまっすぐ進む
光は基本的に直線で進みます。
影ができるのも、どこから光が差しているかが分かるのも、この性質のおかげです。
反射・屈折・散乱
- 反射:鏡に自分が映るのは、光がはね返るから。
- 屈折:コップの水に入れたストローが曲がって見えるのは、光が曲がるから。
- 散乱:空が青いのも、夕方赤く見えるのも、空気中で光が散らばるから。
光の速さ
光は秒速約30万キロメートル。
🌎地球を7周半できるほどのスピードです。
光の速さで火星まで何分?
火星まで光が届く時間は、地球と火星の距離によって変わります。
地球と火星の距離は 約5,600万 km(最接近時)〜約4億 km(遠い時) とかなり差があります。
光の速さ(秒速約30万 km)で計算してみると…
・最接近時(約5,600万 km)
56,000,000 km ÷ 300,000 km/秒 = 約 187秒(3分ちょっと)
・平均距離(約2億2,500万 km)
225,000,000 km ÷ 300,000 km/秒 = 約 750秒(12分半)
・最遠時(約4億 km)
400,000,000 km ÷ 300,000 km/秒 = 約 1,333秒(22分ちょっと)
だいたい3分〜22分、平均すると12〜13分くらいかかるんですね。
色の仕組み
白い光は、実はたくさんの色の光が混ざってできています。
プリズムや雨上がりの水滴で虹が見えるのはその証拠です。
光を使った面白い発見
✨Foldscope(紙の顕微鏡):
紙を折って作れる安価な顕微鏡。光の屈折や透過を使って小さな世界を観察できます。
✨LED(発光ダイオード):
省エネで長持ちする照明。青色LEDの発明で、今の照明技術が一気に進化しました。
✨光集束装置:
望遠鏡で遠くの星の光を集める仕組み。弱い光を逃さずキャッチできます。
🌈光について学べる博物館・イベント
- 科学技術館(東京都):
レンズや電磁波など、光にまつわる体験展示が豊富。 - 千葉市科学館(千葉県):
プラネタリウムと体験型展示が充実し、光や色の仕組みを親子で楽しく学べる。 - パナソニック キッズスクール(オンライン):
子ども向けに光の性質をわかりやすく解説している教材。 - 光ミュージアム(岐阜県):
光をテーマにした展示やアートを体験できる。
まとめ ― 自由研究のヒント
光の不思議は、実験や観察を通じて見えるテーマなので、親子の自由研究にピッタリです。
- 空の色を毎日写真に撮って比べる(朝・昼・夕方)
👉青空や夕焼けの色の違いから「光の散乱の違い」に気づける - コップの水にストローやスプーンを入れて覗く
👉屈折で「曲がって見える」ことを体験できる - CDやプリズムを使って、光の色を分けてみる
👉白い光がたくさんの色でできていることがわかる
こうした身近な体験をまとめれば、きっと楽しい研究発表になるはずです。